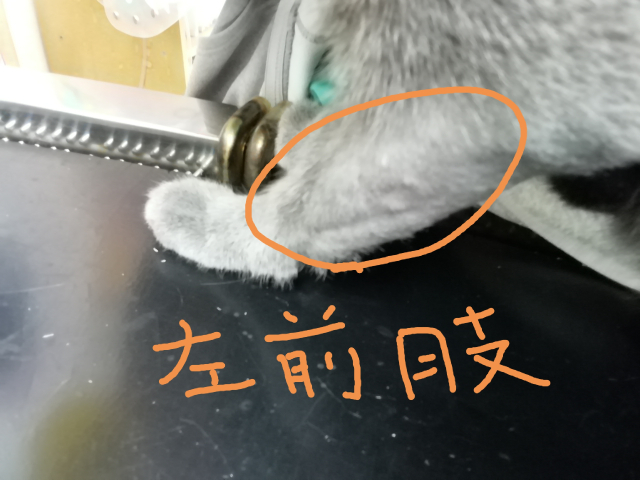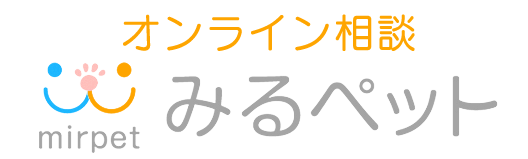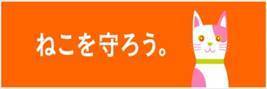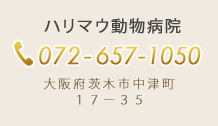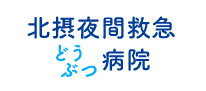―― メーカーの設計思想と、実際の代謝の話 ――
糖尿病の猫ちゃんに処方される「糖コントロールフード」。
メーカーの説明では、
「炭水化物の種類と量を調整し、糖の吸収をゆるやかにして血糖値を安定させる」これは人や犬の“低GI療法”の発想に近く、「食後の血糖の上昇をゆるやかにする」ことで、膵臓への負担を減らす考え方です。
とされています。
この説明は決して間違いではありません。
実際、炭水化物の内容や食物繊維のバランスは、血糖変動の安定に役立ちます。
ただ、猫の場合は少し事情が違います。
猫はもともと、糖を早く吸収する能力が低く、食後の血糖上昇も人や犬ほど大きくありません。
唾液に※アミラーゼをほとんど含まず、膵アミラーゼ活性も犬の10分の1以下。
※糖分を分解
つまり、猫では“吸収をゆるやかにする”というより、「糖を入れすぎないようにする」ことが本質になります。
メーカーの考え方と、猫の体の仕組みの実際
メーカーの言う「吸収をゆるやかにする」は、猫にとっても理にかなっています。
糖をいきなり多く入れない工夫は、確かに代謝を助けます。
ただ臨床の現場では、それに加えて「糖の総量負荷を抑える」ことがより重要になります。
猫は糖を食べて得る動物ではなく、たんぱく質から糖を作り出す動物。
そのため、炭水化物を控え、たんぱく質をしっかり摂ることで、
本来の“自分で糖を作って使う”代謝バランスを守ることができます。
つまり――メーカーの言う「吸収をゆるやかに」は、猫にとっては「糖の量を入れすぎない」という意味に近いのです。
どちらの説明も、向いている方向は同じ。
「血糖を乱さず、体にムリをかけない」筋肉を守る=糖を守る
そのための設計、という点では一致しています。
もうひとつ、糖コントロールで大切なのは「高たんぱく設計」です。
筋肉は糖を“使う場所”であり、また糖を“作る材料”でもあります。
筋肉が減ると、糖を使う力も、作る力も弱まります。
だからこそ、筋肉を守ることが血糖を守ることにつながります。
糖コントロールフードは、高たんぱくで筋肉を維持し、体が無理なく糖を扱えるように設計されています。
まとめ:ふたつの視点は矛盾しない
メーカーの説明:
「糖の吸収をゆるやかにして血糖を安定させる」この二つは、実は同じ方向を向いています。
獣医師の補足:
「猫ではもともと吸収はゆるやか。大切なのは糖の総量を抑え、体の中でムリをさせないこと。」
猫の糖コントロールとは、**“糖を食べさせすぎず・無理をさせず・糖代謝を本来のリズムに戻してあげる”**こと。
それが、体にやさしい本当の意味での“血糖を整える”ということなのです。