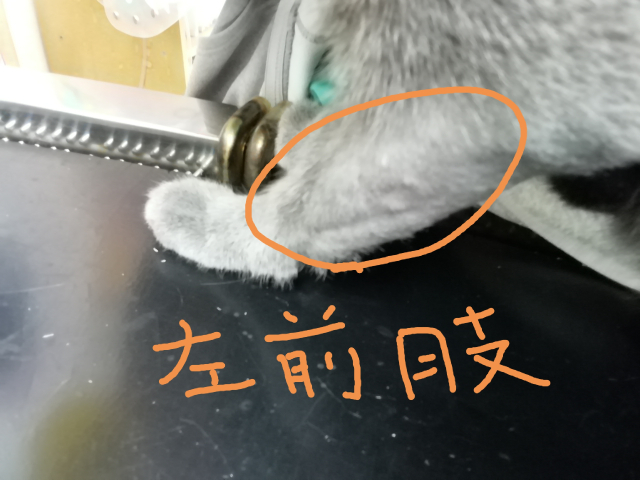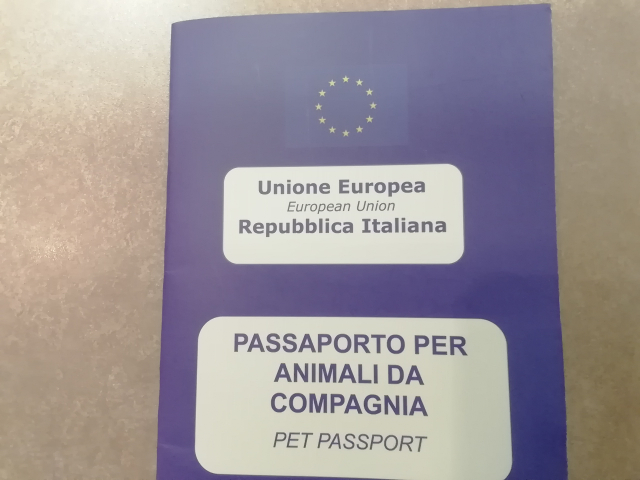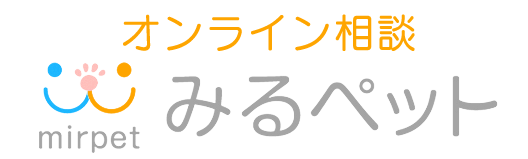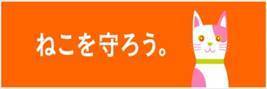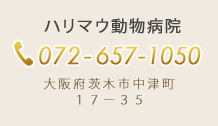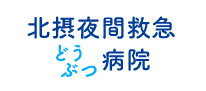朝食の食パンから始まった疑問
※今日はダラダラと長い文章が続きます・・・ごめんなさいね。
朝、いつもの食パンを食べながら、ふと思いました。
「食パン1枚だけでも、血糖スパイクって起こるのかな」と。
“血糖値スパイク”とは、食後に血糖値が急上昇し、
そのあと急激に下がる現象のこと。
こうした血糖の乱高下が糖尿病のリスクを高めるといわれています。
そんなことを思いながらパンをかじっていたら、
頭に浮かんだのは――猫の糖代謝のことでした。
猫は糖を「食べる」より「作って使う」
野生の猫は、炭水化物(糖)をほとんど食べません。
それでも体のエネルギー源として糖を使えるのは、
糖新生(とうしんせい)という仕組みが常に働いているからです。
糖新生とは、食べたたんぱく質を分解して得たアミノ酸から、
自分で糖を作り出す働きのこと。
つまり猫は、「糖を食べる動物」ではなく、
「糖を作って使う動物」なのです
。
この“糖を自前でまかなう”代謝設計こそ、
人や犬とはまったく異なる――
猫という生きものの生命戦略です。
食後も止まらない、猫の“燃料工場”
糖新生は猫だけの特別な仕組みではありません。
人や犬にもあります。
ただし、人や犬では食事をして血糖値が上がると、
「もう糖を作る必要はない」と肝臓が判断し、糖新生はいったん休止します。
ところが、猫ではそれが止まりません。
食後でも糖新生が続くことが知られています。
なぜかというと――猫はそもそも「糖を食べない」動物だから。
炭水化物が少ないため、食後に入ってくる糖が十分でないのです。
そのため、肝臓は「糖を作る」という仕事をやめられないのです。
犬と猫の“燃料工場”のちがい
犬にとっての主な燃料工場は腸。
食べた炭水化物を吸収して糖を得ています。
糖新生はあくまで“補助の工場”であり、
飢餓など非常時に稼働するバックアップの仕組みです。
いっぽう猫ではこの構図が逆。
糖新生こそが日常的に動き続ける“メインの燃料工場”。
つまり猫は、食べた糖に頼らず――
たんぱく質から自ら糖を生み出して生きているのです。
ドライフードと炭水化物
現代の猫たちは、ドライフード誕生前とはまったく違う食生活をしています。
ドライフードの誕生は、人間の“便利さ”のため。
保存性を高め、粒を成形するために、でんぷんなどの炭水化物が必要でした。
その割合はおおむね30〜40%前後。
つまり、本来ほとんど糖質を摂らなかった猫が、
毎日の食事から糖を摂るようになった――
それが現代の猫たちの代謝環境の変化です。
ただしこれをもって
「ドライフード中の炭水化物が糖尿病の直接原因」と言っているわけではありません。
しかし、炭水化物の多い食事は血糖を上げやすく、
それが長く続くとインスリンの効きが悪くなる――
つまりインスリン抵抗性を招くことがあります。
猫の糖尿病とは
猫はもともと、炭水化物をあまり食べない動物です。
そのため、インスリンを使って糖を処理する力がもともと控えめ。
そこへ肥満や高カロリー食が加わると、
その
控えめな仕組みに負担がかかり、インスリンが効きにくくなります。体がインスリンに反応しにくくなると、血糖は高いまま。
すると体は「もっとインスリンを出せば下がるはず」と思い込み、
膵臓に過剰な負担をかけてしまいます。
高血糖の本当の原因はインスリンが“足りない”ことではなく、“効きにくい”ことなのに。
そのため
膵臓は疲れ、やがてインスリンを作る力そのものが弱まります。この2つが重なったとき――糖尿病が起こります。
しかし、猫の糖尿病には希望があります。
インスリンの「効きにくさ」が中心の病気であるため、
早期の治療と体重・食事管理によって、
膵臓が力を取り戻す寛解が期待できるのです。
いっぽう犬では、多くが膵臓のβ細胞が壊れるタイプ(1型)に近く、
残念ながら寛解は難しいとされています。
インスリン抵抗性とは
インスリンは、血糖を細胞の中に運ぶ鍵のようなホルモンです。
通常なら、鍵(インスリン)が鍵穴(細胞の受容体)に入るとドアが開き、糖が入ります。
しかし抵抗性の状態では、鍵穴がしぶく、なかなか回らない。
まるで、鍵穴の油が切れたような状態です。
鍵はある。
鍵穴もある。
でも、うまく回らない。
それが「インスリンが効きにくくなった」状態です。
猫では「油切れ」が戻せることがある
猫の糖尿病の多くは2型に近いタイプ。
鍵穴(受容体)が壊れているわけでも、
鍵(インスリン)を作る力が完全に失われたわけでもありません。
適切なインスリン治療と食事・体重管理により、
鍵穴の動き(感受性)が改善し、
膵臓の疲れが回復することで、
再び自力で血糖を保てるようになることがあります。
報告によって差はありますが、
およそ20〜40%の猫で寛解が見られるとされています。
ケトン体と代謝のバランス
糖尿病が進むと、「糖があるのに使えない」状態になります。
細胞はエネルギー不足と勘違いし、脂肪をどんどん分解し始めます。
そのとき生まれるのがケトン体。
ケトン体は糖の代わりに使われる“もうひとつの燃料”。
猫はもともと炭水化物をあまり食べないため、
脂肪からエネルギーを得る仕組みが日常的に動いています。
つまり猫は、ケトンを作る工場が低速で常に稼働している動物。
それ自体は正常です。
ただし、糖が使えなくなるとこの仕組みが暴走し、
血液が酸性に傾く糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)に進むことがあります。
猫はこの「ケトン工場」が常に動いているぶん、
バランスを崩すとDKAに進むスピードが速いともいわれます。
静かで繊細な代謝の世界が、
ほんの少しの崩れで一気に暴走する――
それが猫の糖尿病の怖さです。
まとめ
・猫は「糖を食べる」より「糖を作る」動物。
・糖新生は食後も続き、日常代謝の一部になっている。
・ドライフードの炭水化物は血糖を上げやすく、
長期的にインスリン抵抗性や膵臓疲弊を助長しうる。
・「インスリンに鈍い」とは、鍵穴の油切れのような状態。
・猫では、その“油切れ”が治療で戻ることがある(=寛解)。
・ケトン体は正常代謝の一部だが、暴走すると危険。
結び
猫の糖尿病は、血糖を下げることだけに注力していれば治る病気ではありません。
数字の向こうで、少し重くなった代謝の歯車を整えていく――
それが、この病気の本当の治療です。
焦らず、時間をかけて、
猫が本来もっているリズムを取り戻していく。
その積み重ねが、治療のすべてです。
猫は、静かに体の中で、今日も確かに
糖を作り、燃やし、また作りながら、生きるリズムを刻んでいます。
私たちができるのは、そのリズムを壊さずに見守ることです。