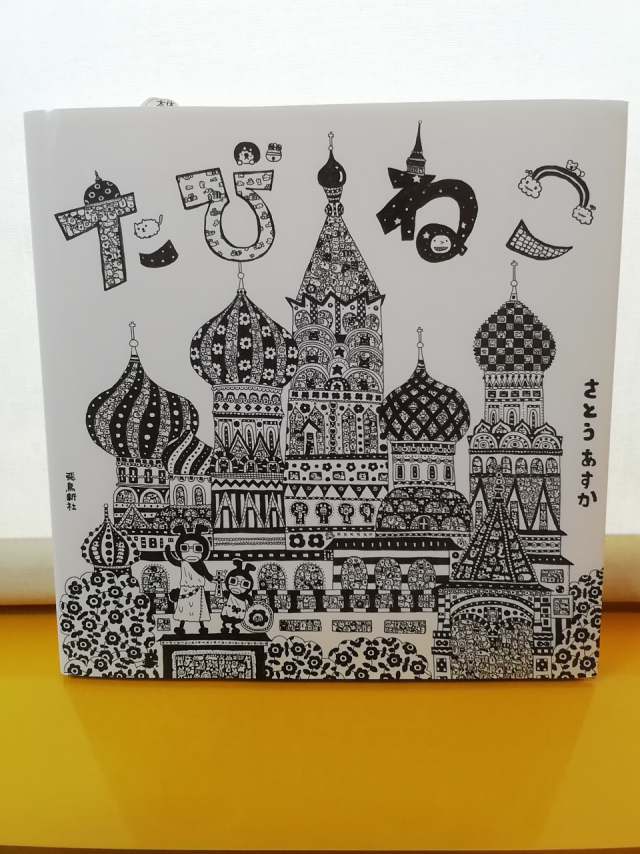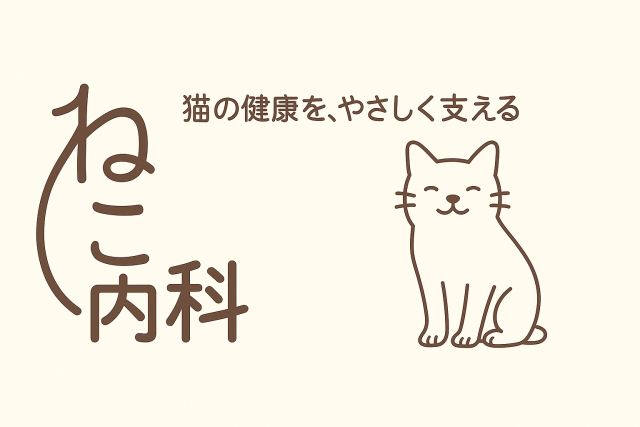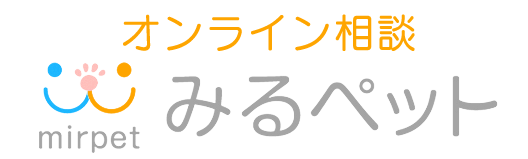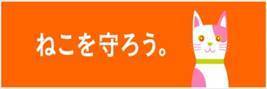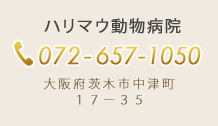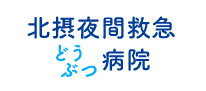いよいよ夏本番という感じで、蒸し暑い日が続いていますね。
先週の7月12日、開院前の準備中に、今年初めてセミの声が聞こえてきました。
いよいよ来たな……と、ちょっと身構える音でした。
この日は土曜日で診察は午前中のみ。
診察が終わった後、妻が「万博公園にブルーインパルスが飛んでくるみたい。見に行ってみる?」と。
ここ最近は家と病院の往復だけ、ずっとエアコンの効いた室内で過ごしていたので、急に炎天下はちょっと不安でしたが……思い切って病院から自転車で出かけました。
途中少しクラクラっとして、「これはちょっと危ないかも」と思いながらも、「いや、昔は野球部だったし(ずいぶん昔だけど)」と自分に言い聞かせて、なんとか万博公園へ。
今回の飛行は、関西万博が折り返し地点に入ったことを記念した、ブルーインパルスの大阪一周飛行だったようです。
関空を出発し、舞洲→万博会場→通天閣→大阪城→太陽の塔(旧万博)と北上し、ひらパー(ひらかたパーク)で折り返すというルート。
ちなみに関西の方ならおなじみかもしれませんが、私たちが向かったのは「旧万博」、太陽の塔がある万博記念公園の方です。
真上を通過!塔の裏手で見た特等席
公園に着くと、すでにたくさんの人が集まっていました。
特に太陽の塔の正面側は、スマートフォンを構えて空を見上げる人でいっぱい。
木陰などもすでに埋まっていたので、私たちは塔の裏手の広場へ。
結果的に、この裏手の位置こそが、ブルーインパルスが真上を通るベストスポットでした。
これがまさに大正解。
スマホを見ていた人たちから「関空、飛び立ったみたい」との声。
そこから10分ほどして、午後2時40分ごろ、「きた!」というざわめきとともに北西の空にブルーインパルスが登場。
そして、白煙を引きながら自分たちの真上を駆け抜けていった瞬間には、ただただ圧倒されて見上げるしかありませんでした。
小学生だったら目指す進路が変わっていたかも
もし自分が小学生だったら、「将来はブルーインパルスに乗る! 獣医さんじゃなくて!」って言ってたかもしれません。
ここ数年でいちばん感動した出来事でした。
暑さに文句を言いながらも、見に行こうと連れ出してくれた妻には感謝です。
帰り道、マカロンアイスを買って、隣接するららぽーとでしばらく涼んでから帰宅しました。
久しぶりに、夏らしい午後を過ごした気がします。